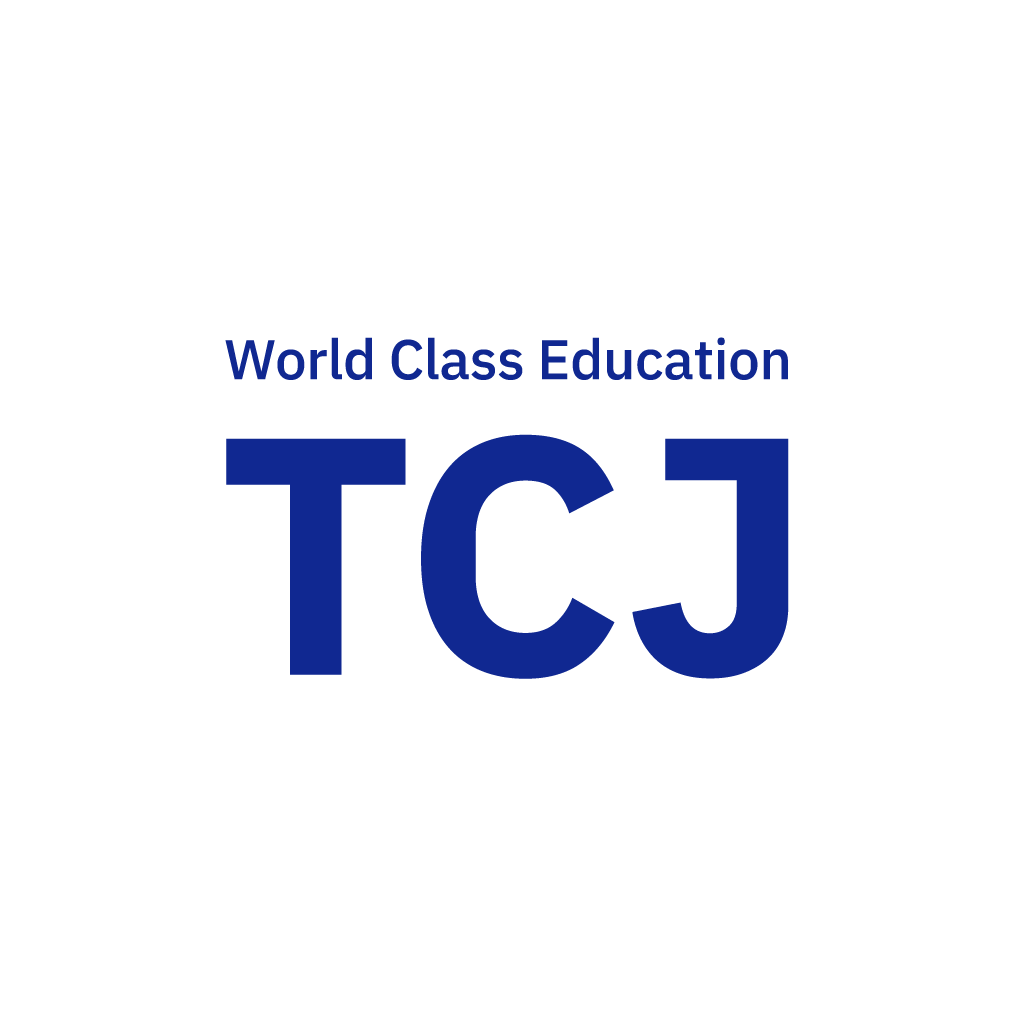大塚 三喜男氏 有限責任監査法人トーマツ マネジャー
今回(第3回)から第5回までは、日本基準とIFRSの収益認識規準の違いについてご紹介します。
1.カスタマー・ロイヤルティ・プログラムとは?
前回(第3回)から第5回までは、日本基準とIFRSの収益認識規準の違いについてご紹介していますが、今回は収益認識の中でも特殊論点であるカスタマー・ロイヤルティ・プログラムについて取り上げたいと思います。
カスタマー・ロイヤルティとは、「販売取引の一部として顧客が物品やサービスの購入に対するインセンティブとして付与する特典(以下、特典クレジット)」のことを指します。具体的な例では、航空会社のマイレージや家電量販店のポイント、携帯電話会社が利用料金に応じて顧客に付与するポイントなどが特典クレジットに該当します。対して、商品やサービスの販売と関係なく街頭で不特定多数に対して配布される割引クーポンなどは、販売取引の一部を構成しないことから特典クレジットには該当しません。
昨今ではIFRS に関する情報が多くの書籍・紙面で取り上げられ、「ポイント会計」や「ポイント引当金」といった用語が目につくようになりました。なぜこれらの言葉が脚光を浴びるようになったのかについては後述しますが、あくまで現時点における日本の会計基準もしくはそれに準じたもので、特典クレジットにかかる会計処理を特別に規定したものは存在しません。日本公認会計士協会より平成21年7月9日付で公表された企業会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS 第18号に照らした考察-」(平成21年12月8日最終改正)においてポイントの会計処理についての記載が存在しますが、あくまで研究報告であり、会計処理に対する強制力を有していないのが実情です。そのため、従前は特段の指針が無いことから、会計の一般原則の枠内において、各企業の判断に基づき会計処理を行っていたため、引当金や未払費用等の科目で処理を行ったり、販売時にポイント利用相当額の全てを値引として処理を行うケースが多かったものと想像されます。
2.IFRIC第13号の設定経緯
ここで少し話は変わりますが、この特典クレジットに係る会計処理はIFRIC第13号という解釈指針で規定されています。この“IFRIC”について少しお話ししようと思います。
まず、IFRICとは基準書ではなく、解釈指針とされています。これらが設定されるのは、基本となる会計基準書(IASやIFRS)に基づいて取引の実態を考えた場合に、複数の合理的な会計処理が考えられ、かつ、それらの選択しうる複数の会計処理を行った結果の間に重要な差が生じる場合です。なお、解釈指針とは言え、会計処理に対する強制力を有しているため、これらに準拠しない会計処理は認められません。
IFRSには、IFRIC第13号(2008年7月1日以後開始事業年度より適用)が発行されるまで、特典クレジットについて特別に規定した会計基準が存在しなかったことから、特典クレジットを付与しているIFRS 適用企業が従前において会計処理を行うに際しては、収益の基準書であるIAS第18号に基づき、
(1) 販売取引で受領したか又は受領し得る対価の一部を特典クレジットに配分し、収益の認識を繰り延べる(IAS第18号第13項適用)
(2)特典の提供のための見積将来コストを引き当てる(IAS第18号第19項)
の2通りの選択肢が考えられました。
この2通りの選択肢を採用した場合のそれぞれの会計処理結果はどうなるかと言えば、(1)の場合は繰延収益の概念のため、売価を基礎とした金額で負債計上されるのに対して、(2)の場合は引当金、もしくは未払費用等の概念のため追加原価や支出額を基礎とした金額で負債計上されることになり、結果として双方の負債として認識される金額に大きな差異が生じることになります。
実際のところ、既にIFRSに移行している欧州上場企業の多くで(2)が採用されていたものと想像されますが、具体的な指針のない中で実務が多様化したこと、すなわち、潜在的かつ重要な差異の存在が企業間の比較可能性を損ねるものとしてIFRIC第13号が設定されることとなったというのは想像に難くありません。
3.特典クレジットの会計処理
このような流れを受け、IFRIC第13号では、特典クレジットの会計処理として前項の(1)の考え方を採用することを義務付けました。すなわち、特典クレジットの付与を行う売上取引を「複数の構成要素を含む売上取引」として捉え、「財貨又はサービスの提供」と、「それに伴い発生する特典クレジットの付与」を別個の売上取引として、それぞれを公正価値で認識すべきという考え方です。
ここで言う公正価値とは、独立第三者間取引において、取引の知識がある自発的な当事者の間で、資産が交換され得る又は負債が決済され得る金額として定義されますが、平たく言えば一般的な売価を想像していただければわかりやすいかと思います。
典型的な例として航空券の販売取引を考えてみましょう。仮にある航空券の購入者が航空会社のマイレージプログラムに加入していれば、航空券の販売に伴い、搭乗した区間等に応じたマイルが付与されることになります。この場合、航空券の販売代金の総額には、航空券自体の対価と、付与されるマイルの対価の双方が含まれるとみなされ、それぞれを区分して公正価値で会計処理します。なお、付与されたマイルの公正価値は将来のマイルの交換に伴い提供されるサービスの公正価値に基づき測定され、繰延収益として負債に計上されます。
4.実務への影響
それでは特典クレジットの会計処理を行うに際してどのような問題が生じるでしょうか。おそらく、まず直面するであろう問題が、「特典クレジットの公正価値をどのように見積るか」という問題です。特典クレジットの会計処理を行うにあたっては、通常の販売取引の対価を複数に区分することが必要であり、その結果、按分する基礎となる総額、すなわち、この場合はマイルの付与を伴う航空券の販売価格は割と容易に判明します。これに対して、相手勘定である売上高(航空券のみ)と繰延収益(航空券の購入に伴い付与されるマイル)の公正価値をどのように測定するかについては、公正価値が直接入手可能でない限り、見積りが要求されます。IFRIC 第13 号では、特典クレジットの公正価値の見積りを行うにあたり、その交換対象となるサービスの公正価値を参照すべきとしていますが、航空券に同一サービス内容の格安運賃が設定されているように、現実には同一のサービスに対して複数の販売価格が設定されている場合や、直接的に公正価値が把握困難である場合も多く、その結果、公正価値の見積りの基礎としてどの金額を採用するかで繰延収益の金額が大幅に変わる可能性があります。
次に、見積りを行うにあたり必要となる情報が入手可能か、という問題があります。IFRIC第13号では、特典クレジットの交換対象サービスを受益者側が選択可能な場合においては、各サービスの公正価値の加重平均に基づき特典クレジットの公正価値を見積ることとされています。このような計算を行うにあたっては、見積りの基礎として過去における詳細な実績データを参考にする必要があるため、過去のデータを収集可能な体制を事前に整えることが必要と考えられます。
さらに、繰延収益の考え方が採用されていることから、繰り延べた収益とそれに対する取り崩しを対応させて把握することが必要になります。と言うのも、繰延収益は収益を繰り延べた時点における公正価値で測定され、経営者の見積りの変更を要因とした事後的な変動は繰延収益の金額に影響させないため、期末において特典クレジットの金額を一括で評価替することは原則としてできません。このような年間の特典クレジットの付与と償還のフローをどのように紐付けて把握するかについては、システムでの対応が必要となる場合があります。
5.終わりに
最後に、従来、原価を基礎として特典クレジットの会計処理を実施していた企業がIFRIC第13号を適用した場合の影響について少し触れたいと思います。
もちろん、影響の大小についてはその企業の属する業種や、提供している特典クレジットのプログラムに応じて大きく異なりますが、例えば、欧州の某航空会社では、負債計上額が1,000億円以上(適用時の為替相場に基づく)増加する結果となっており、特典クレジットを付与している各企業にとって少なからず影響があることは容易に想像できます。このように、IFRS 導入に伴い、財務数値に大きな影響を与える要因として、日本においても「ポイント引当金」等の言葉が紙面を賑わすようになっており、その影響を受けるであろう、企業の付与するポイントの市場規模はいまや1兆円(日本経済新聞2009年7月30日)とも言われています。
上記のように、確かにIFRIC 第13号の導入によって、負債が大幅に増加することが想定される企業もありますが、IFRIC第13号適用に伴う負債の増加は企業の隠れた債務の顕在化では無いものと考えています。なぜなら、従前の特典クレジットの会計処理に複数の選択肢があったことからわかるように、「将来いくらの売上高が控除されるか」という繰延収益としての考え方も理論的であるのと同様に、多くの企業が採用していたであろう「将来いくらの支出が生じるか」という原価を基礎とした考え方も理論的であるためです。
IFRS導入には、とかくネガティブな印象がつきまといがちですが、ことこの件については、繰延収益と原価の2つの側面から特典クレジットを継続的に捉えることで、むしろ企業にとって中長期的なポイントプログラムの運営方針を決定す る有益な判断材料をもたらすことになるかもしれません。
文中意見にわたる部分は執筆者の個人的な見解であり、執筆者の属する組織の公式な見解ではありません。
(第5回に続く)